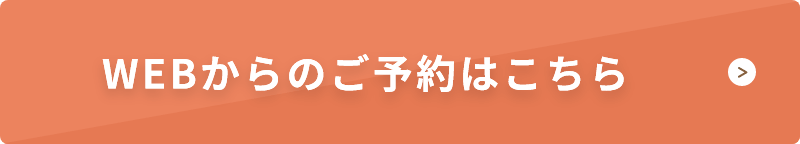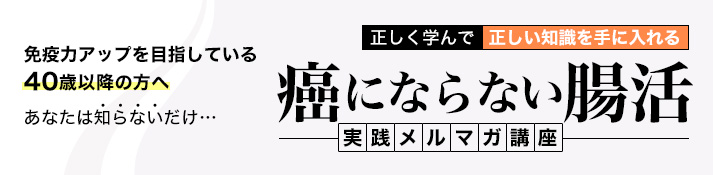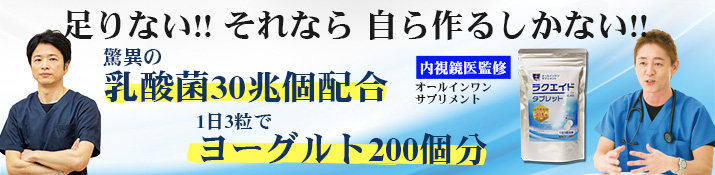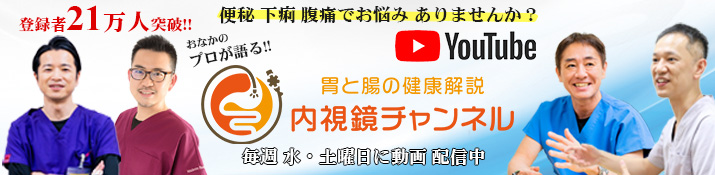MENU
閉じる
たまプラーザ南口胃腸内科クリニックブログ
Clinic Blog

健康診断のオプション検査の注意点
2025年04月06日
- 副院長ブログ
こんにちは。副院長の東です。
桜が満開に咲いていますね。
雨の期間も短く例年よりも桜が長く咲いていて、とても嬉しいです。
新年度の良いスタートを出来ましたか?
健康診断のオプション検査の注意点
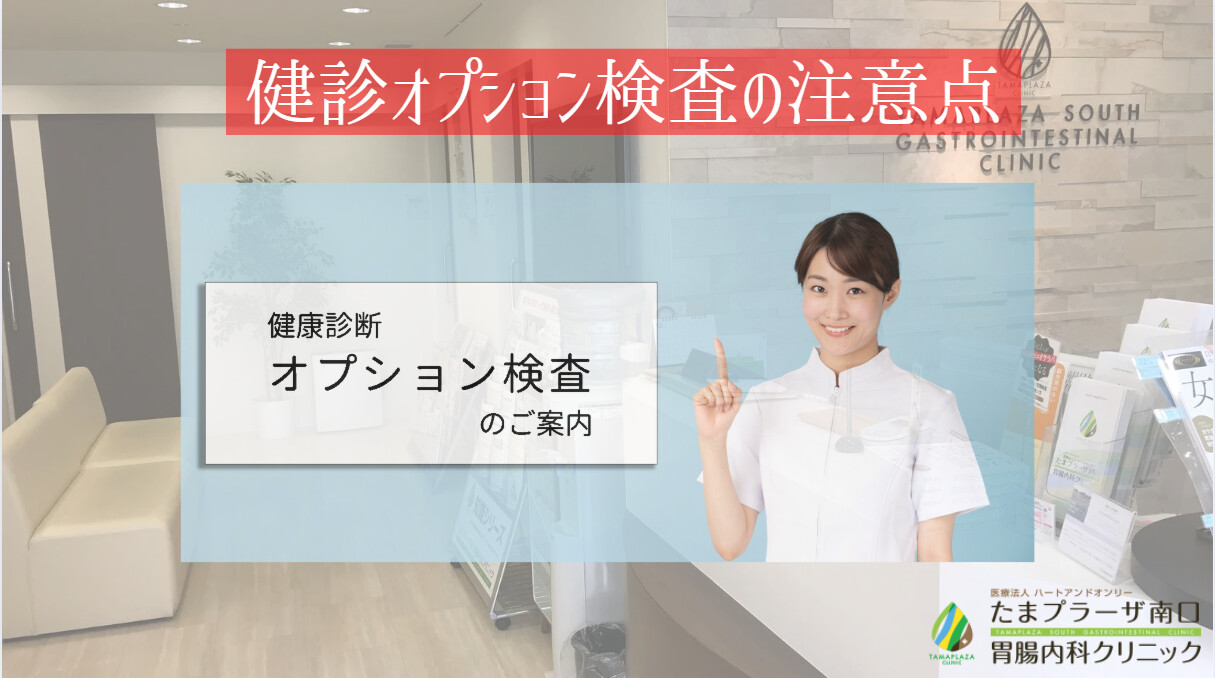
春の季節は、定期健康診断が行われます。
企業や学校によって時期は異なりますが、4~5月に行われることが多いと思います。
健診企業が来てくれるタイプ、自分で予約して訪問するタイプとあります。
基本健診に加えて多種多様のオプションがあり困ることが多いかもしれません。
基本健診では、身長体重、腹囲測定、視力聴力検査、血液検査、尿検査、診察が必須で、
年齢に応じて便潜血検査、心電図測定、胸部X線検査、胃X線検査(胃内視鏡)が加わります。
基本健診の内容が異なるのは、主に所属する企業、学校側の健康保険組合の健診への力の入れ方が違うのではないかと。
充実していればラッキーだし、不足していれば追加するものありです。
オプション項目では、どの項目を選択したらよいか迷いますよね?
今日は、注意点を2点挙げてみたいと思います。
✓ 血中ピロリ抗体
一般的にピロリ菌の感染は5歳までの時期に起こります。
抗体価3未満であればピロリ菌未感染と考えられます。内視鏡で胃粘膜の萎縮がないことを確認できれば確実です。
ピロリ菌の感染による萎縮性胃炎が胃内に全体に広範囲に拡がっている場合、
自然とピロリ菌がいなくなり抗体価が陰性化する事があるので注意が必要です。
ピロリ菌除菌後も抗体価は徐々に低下し正常化してきます。
血中ピロリ抗体を毎年選択されている方がいますが、一度測定すれば良いので必要ありません。
10以上であればピロリ菌感染が疑わしいので、必ず胃内視鏡検査を受けるようにしましょう。
3から10の場合は、陰性高値といい、ピロリ菌の感染がある可能性が否定できない状態です。
抗体は、体内で産生する免疫物質であり、ピロリ菌そのものを診ている訳れはありません。
胃内視鏡検査による胃粘膜の状態の確認、必要あれば尿素呼気試験等でピロリ菌の感染の有無を調べます。
✓腫瘍マーカー
がんマーカーともいわれる腫瘍マーカーは、オプション項目の代表選手です。
血液検査で「がん」が産生する物質を測定します。
数値が高ければ「がん」が存在する可能性があるとの考えから、よく選択されています。
健診で引っかかってくる腫瘍マーカーのほとんどは、基準値からごく僅かに外れた値です。
例えば消化器系ではCEAは5.0が基準値ですが、5.1で陽性と判定されます。
CA19-9は37が基準値ですが、40とか。
私たちが通常診療の中で、腫瘍マーカーを測定する時がいつかご存じですか?
それは、がんと診断した時なのです。
がんが産生する値なので、がん細胞数が多ければ腫瘍マーカーの値が比例的に高くなります。
しかしながら、早期がんでは腫瘍マーカーの上昇はほとんどありません。
進行がんの場合は、多くが腫瘍マーカーの桁が変わります。
つまり、CEAやCA19-9ならば100以上、1000以上のこともあります。
がんが小さくなれば、上昇していた腫瘍マーカーは低下していきます。
手術や抗がん剤などの治療効果を推定するための値だと考えましょう。
注意点のもう一つは、腫瘍マーカーが上がらない場合もあるので、がんで100%陽性にならないことです。
健診は自分の健康状態を知る良い機会です。
異常が出た場合には、何か病気が隠れているリスクがあります。
経過観察でよい場合が多いですが、早期治療に結びつけれられる機会かもしれません。
しっかりと健診を受けましょう。
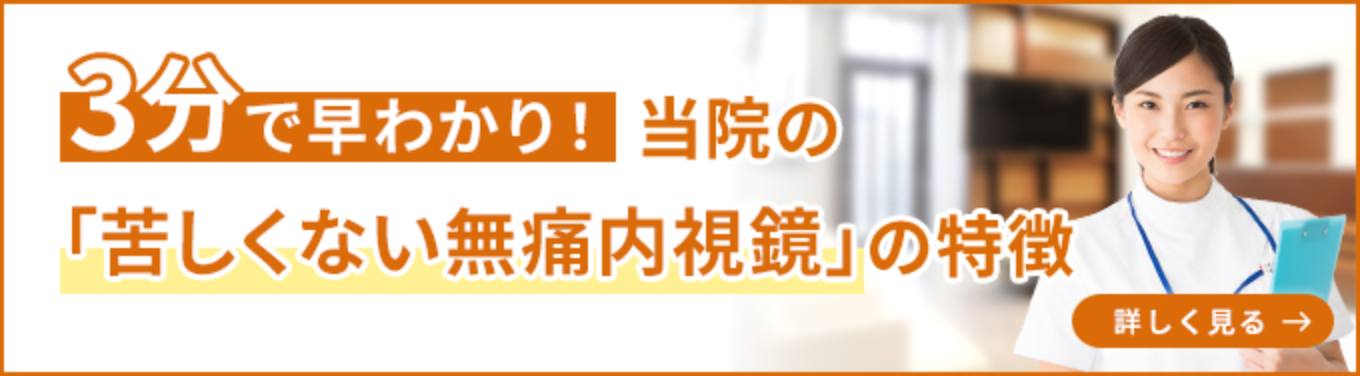
この記事を書いた人

東 瑞智
医師
北里大学医学部を卒業。北里大学病院消化器内科学講師として、消化器がんの内視鏡診断・治療、抗がん剤治療だけでなく、難治性逆流性食道炎、機能性ディスペプシア、過敏性腸症候群などの消化器良性疾患の治療に従事。2020年より、たまプラーザ南口胃腸内科クリニック勤務。北里大学医学部消化器内科学非常勤講師。