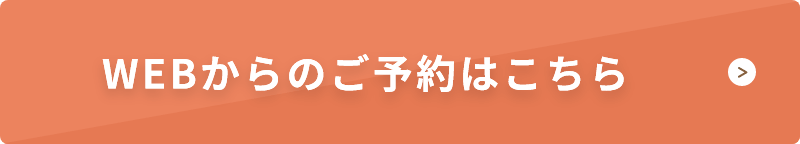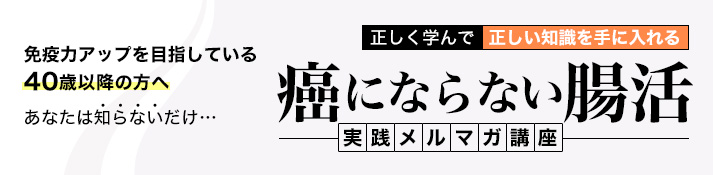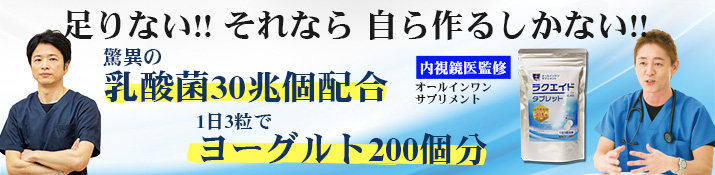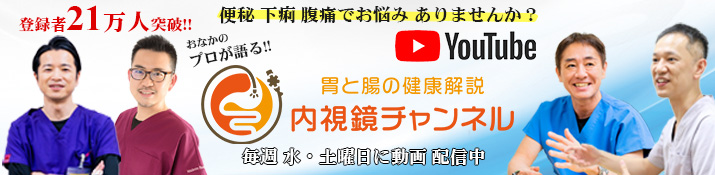MENU
閉じる
たまプラーザ南口胃腸内科クリニックブログ
Clinic Blog

過敏性腸症候群?!
2025年04月20日
- 副院長ブログ
こんにちは。副院長の東です。
春らしい暖かい気候で心地よいですね。
もうすぐGWです。
過敏性腸症候群?!

新年度が始まっています。
従来から環境の変化のない方も、新しい環境で始まった方もいると思います。
人の入れ替わりは必ずあり、人間関係の構築を一から始める方も多いのではないでしょうか?
社会生活の中で、環境の変化は大きなストレスになり得ます。
自律神経のバランスが崩れて、精神的な影響から肉体的に影響をきたすことも多いものです。
特段、胃腸の働きはこのストレスによる影響を強く受けます。
胃腸の不調があって、内視鏡検査をしても異常はないことも多く見受けられます。
この時の原因として考えられるのが、機能性の異常なのです。
胃であれば、機能性ディスペプシア、腸であれば過敏性腸症候群が考えられます。
腸の役割は、栄養や水分の吸収機能と排便機能です。
腸が動き過ぎれば下痢、動かな過ぎれば便秘になってしまいます。
つまり、働きが一定せず、それが症状として出てしまうことになります。
交代制便通といわれる便秘と下痢を繰り返すパターン。
便秘が主体の便秘型のパターン。
下痢が主体の下痢型のパターン。
外来診療のなかで、自律神経の乱れや過緊張による下痢型が最近は多いと感じています。
過敏性腸症候群は、環境の要因を改善する事からアドバイスしています。
食事、生活習慣、ストレスに原因がないか、改善点がないかを考えていきます。
食生活の改善だけで良くなる方もいます。
過敏性腸症候群の方は、過量の食物繊維摂取で症状が増悪する方もいるので細かな調整が必要な事があります。
そして、内服治療です。
腸内環境を整備するための整腸剤、腸の動きを調整してくれる蠕動運動調整薬、便の水分コントロールをする薬剤など。
過敏性腸症候群の治療は・・・。
完治を目指す治療ではなく、症状をコントロールする治療なのです。
腸の働きを整えていけば、自然と腸の事を気にしなくなっていきます。
その積み重ねが、日々の生活の自信につながっていきます。
過敏性腸症候群は克服できます。
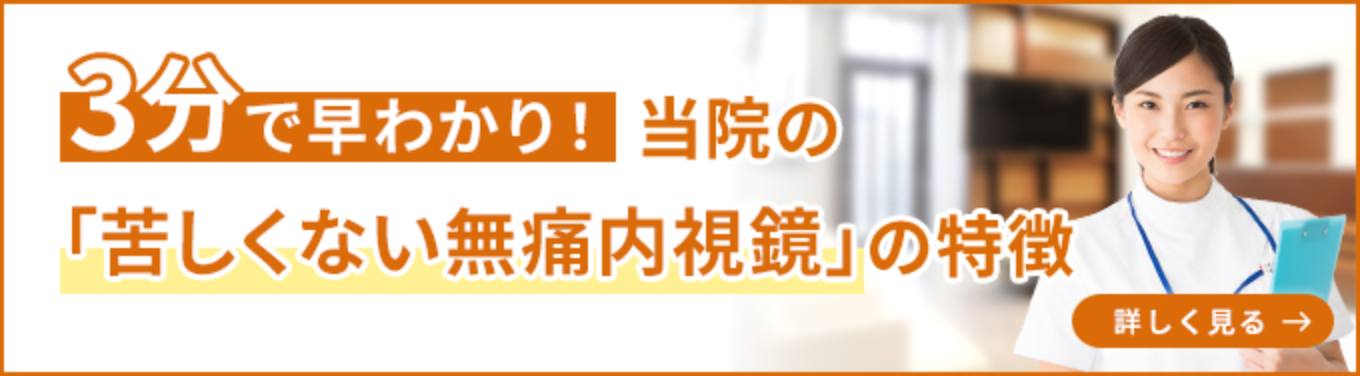
この記事を書いた人

東 瑞智
医師
北里大学医学部を卒業。北里大学病院消化器内科学講師として、消化器がんの内視鏡診断・治療、抗がん剤治療だけでなく、難治性逆流性食道炎、機能性ディスペプシア、過敏性腸症候群などの消化器良性疾患の治療に従事。2020年より、たまプラーザ南口胃腸内科クリニック勤務。北里大学医学部消化器内科学非常勤講師。