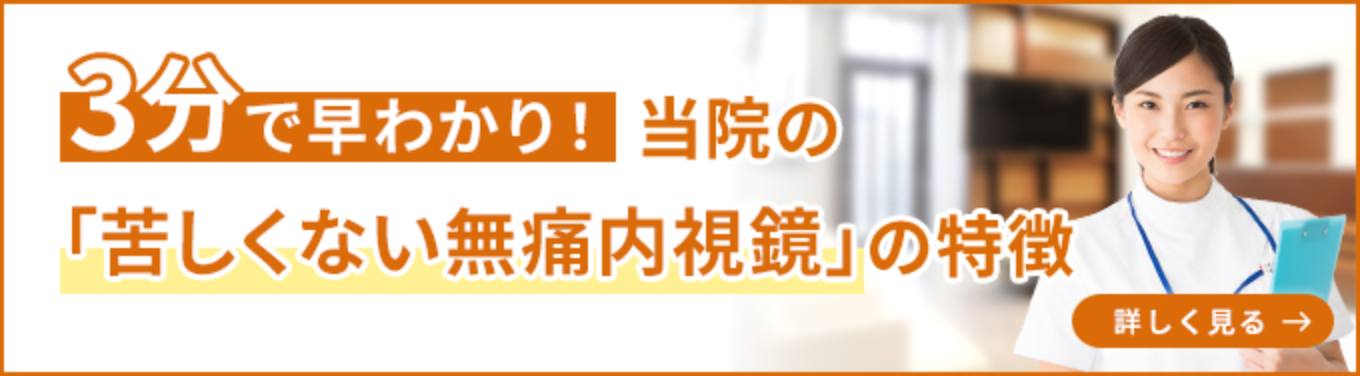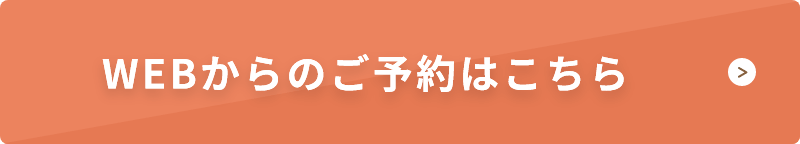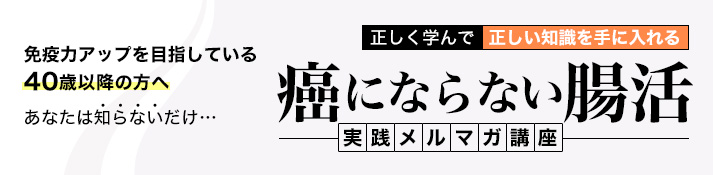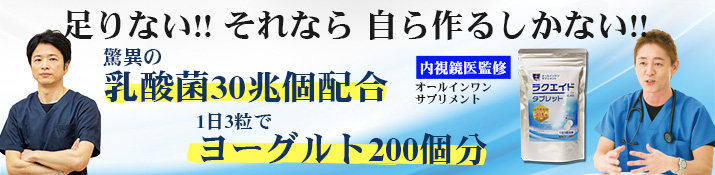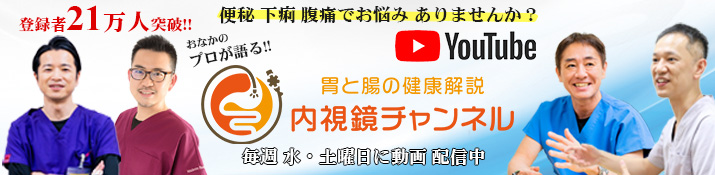MENU
閉じる
おすすめ内視鏡豆知識
Endoscopist Doctor's Knowledge

急性胃腸炎とはどんな病気?その原因や症状、治療方法を解説
急性胃腸炎は、吐き気や腹痛、下痢などが突然起きる病気です。ウイルスや細菌感染、食事に由来する食べ物の影響などさまざまな原因で発症しますが、季節や生活習慣とも関係があります。この急性胃腸炎は誰にでも起こりうる身近な症状なので、もしなってしまっても適切な対処をすることで回復を早めることが可能です。
今回は、急性胃腸炎とはどんな病気なのか?また急性胃腸炎の原因や症状、治療方法についても見ていきます。
1. 急性胃腸炎とは?
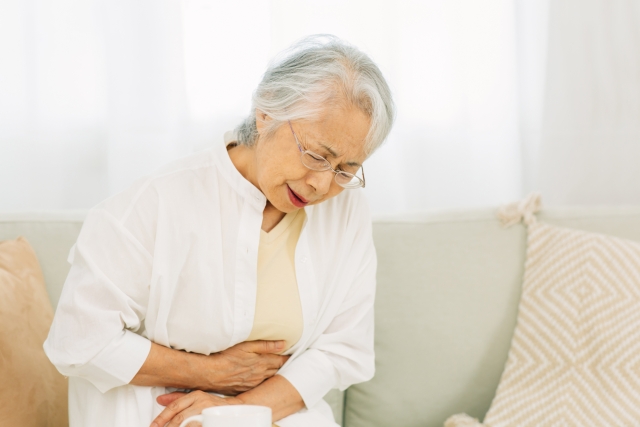
急性胃腸炎は、胃や腸の粘膜が急激に炎症を起こす疾患で、主にウイルスや細菌などの病原体の感染が原因となります。主な症状としては、突然の吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、発熱などがあります。冬にはノロウイルスやロタウイルスによる感染が増加、夏には細菌性の食中毒が多く見られます。
2. 急性胃腸炎の原因

急性胃腸炎の原因には大きく分けて「ウイルス性胃腸炎」「細菌性胃腸炎」「その他の感染性胃腸炎」に分けられます。
2-1. ウイルス性胃腸炎
ウイルス性胃腸炎は、ウイルスの感染によって引き起こされる胃腸の炎症のこと。主な原因ウイルスには、ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスなどがあり、冬から春先にかけて流行する傾向があります。
ノロウイルスはあらゆる年齢層にて感染が見られますが、ロタウイルスは5歳未満の小児での感染が多いとされています。またアデノウイルスは、季節を問わず感染する可能性があります。
これらのウイルスは、感染者の便や嘔吐物、汚染された食品や水を介して経口的に感染します。適切な予防策を講じて、感染拡大を防ぐ必要があります。
2-2. 細菌性胃腸炎
細菌性胃腸炎は、細菌感染によって引き起こされる胃腸の炎症で、食中毒の一種と言われています。特に夏に多く見られるのが特徴です。
主な原因菌として、カンピロバクターやサルモネラ、病原性大腸菌、黄色ブドウ球菌などがありますが、これらの細菌は生卵や生肉、特に加熱が不十分な鶏肉や牛肉の摂取、または調理器具や手指を介した二次感染によって体内に侵入します。
2-3. その他の感染性胃腸炎
上記のウイルス性胃腸炎や細菌性胃腸炎以外に、寄生虫による感染性胃腸炎もあります。たとえば、ランブル鞭毛虫(ジアルジア)やクリプトスポリジウムなどが原因となることがありますが、これらの寄生虫は、汚染された水や食品を摂取することで感染し胃腸炎を引き起こすものです。よって、衛生環境が整っていない地域や状況での感染リスクが高まる点については知っておきましょう。
3. 急性胃腸炎の症状について

急性胃腸炎になると以下のような症状が現れます。
3-1. 吐き気や嘔吐
急性胃腸炎の初期症状として、突然の吐き気や嘔吐が多く認められます。特にウイルス性胃腸炎では頻繁に嘔吐を伴うことがあります。嘔吐は体が異物を排出しようとする防御反応ですが、頻繁に続くと体内の水分や電解質が失われ、脱水症状を引き起こす可能性がありますので、嘔吐が止まらない場合は食事を控えて少量ずつ水分を補給することが大切です。
3-2. 下痢
急性胃腸炎にかかると水様性の下痢が生じ、1日に何度も排便があるケースがあります。特にノロウイルスやロタウイルスによる感染では、大量の水分が含まれた便が出ることが多く、細菌性胃腸炎の場合は粘液や血が混じることがあります。下痢が長引くと体内の水分や塩分が不足しやすくなるため、こまめな水分補給を行いましょう。市販されている経口補水液による脱水、電解質の補正をするのも良いでしょう。
3-3. 腹痛
急性胃腸炎にかかると主に胃や腸の炎症による痛みが生じます。腹痛の程度や部位は人によって異なりますが、ウイルス性胃腸炎では差し込むような痛みがあり、腸の動きが活発になることで強まることがあります。また細菌性胃腸炎では、腸の炎症が激しくなり、持続的な痛みを感じるケースがあります。お腹を温めることで痛みが和らぐこともありますが、痛みが増す場合は早めに医師の診察を受けましょう。
3-4. 発熱
急性胃腸炎では、ウイルスや細菌の影響で発熱を伴うことがあります。ウイルス性胃腸炎の場合は37~38℃の微熱で治まることが多いですが、細菌性胃腸炎の場合、38℃以上の高熱が出ることがあります。特にサルモネラ菌やカンピロバクターによる感染では、高熱とともに悪寒や筋肉痛を伴うこともあるので注意が必要です。発熱時には水分を十分に摂取し、発汗による脱水に気を付けましょう。
3-5. 脱水症状
嘔吐や下痢が続くと体内の水分や塩分が急速に失われ、脱水症状を引き起こします。脱水症状のサインとしては、口の渇きや唇の乾燥、倦怠感、尿量の減少などが見られます。特に乳幼児や高齢者は脱水になりやすく、重度になると意識障害を引き起こすこともあります。
3-6. 食欲不振
急性胃腸炎になると、食欲が低下するのは自然なことです。無理に食べる必要はありませんが、極度のエネルギー不足にならないよう、消化の良いものを少量ずつ摂ることが望ましいとされています。体調をみながら徐々に食事量を増やしていくことが大切です。
4. 急性胃腸炎と間違えやすい病気

急性胃腸炎は、嘔吐や下痢、腹痛などの症状を引き起こしますが、これらの症状は他の疾患と似ているため間違えやすい点に注意しなければなりません。次の紹介する疾患は、急性胃腸炎と間違えやすいものです。
4-1. 虫垂炎
虫垂炎は、初期症状として吐き気や腹痛が見られるもので、特に右下腹部に痛みが集中します。急性胃腸炎と症状が似ていますが、虫垂炎は炎症が波及して腸管穿孔が起こると腹膜炎となり緊急手術が必要となる場合があるため、あまり痛みが引かない場合には。医師の診断を受けましょう。
4-2. 肝炎
急性ウイルス性肝炎にかかると、倦怠感や食欲不振、嘔吐などの症状が現れます。急性胃腸炎と混同しやすいものの、肝炎の場合は黄疸や肝臓の腫大が見られる場合があります。特に黄疸が診られている場合は原因の精密検査が必要なります。血液検査や腹部超音波検査を行う必要があるため早急な医療機関への受診が必要です。
4-3. 膵炎
急性膵炎は、大量のアルコール摂取や、胆石症の嵌頓(かんとん)などにより生じ、上腹部から背中にかけての強い痛み、嘔吐、発熱などが特徴です。急性胃腸炎と症状が似ている部分がありますが、過剰な膵アミラーゼによる膵臓自体の壊死を引き起こし、激しい背部痛を呈する事が大きく異なります。急性膵炎は重篤な合併症を引き起こす可能性があるため、疑いがある場合には早い診断および治療が求められます。
4-4. 炎症性腸疾患(IBD)
潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患(IBD)は、1か月以上の慢性的な下痢や腹痛、血便などが主な症状として現れます。急性胃腸炎と違って症状が長期間続くのが特徴です。
5. 急性胃腸炎の治療方法

急性胃腸炎の治療方法ですが、主に対症療法となり脱水症状の予防や適切な食事管理、必要に応じた薬物療法などが取られます。
5-1. 脱水症状の予防
最も重要なのは脱水症状の予防です。急性胃腸炎にかかり嘔吐や下痢が続くことで体内の水分と電解質が失われてしまうことから、こまめな水分補給は必要です。経口補水液やスポーツドリンクを少しずつ飲むことで、体への負担を減らしながら水分を補給しましょう。
5-2. 食事の管理
急性胃腸炎では食事療法も大切です。症状が落ち着くまでは、胃腸への負担を最小限にするために消化の良い食事(お粥やうどん、バナナなど)を心掛けましょう。反対に脂肪分の多い食品や乳製品、香辛料を多く含む刺激の強い食物は、胃腸に負担をかけるため避けましょう。なお症状が改善した後も、数日は消化の良い食事を続けるのが無難です。
5-3. 薬物療法
薬物療法については基本的に症状が強い時に検討されます。嘔吐がひどい場合には制吐剤を使用することがありますが、医師の指示のもとで適切量を使用する必要があります。なお、下痢を止める薬は、細菌やウイルスを体外に排出する働きを妨げる可能性があるため、服用しないほうがよいとされています。一方で、乳酸菌や酪酸菌などの整腸剤を内服して腸内環境を整えることは、症状改善を助けるための重要な治療のひとつです。
できる限り自己判断で市販薬を服用するのは避け、症状が重いと感じた場合には、速やかに医療機関を受診して適切な治療を受けることが望ましいです。
腸管出血性大腸菌O-157による重症の細菌性胃腸炎の場合は、点滴による補液、抗生剤投与が必要となるので、生の牛肉を生食し、同様の症状の人が多数いて集団食中毒が疑わしい場合は速やかに医療機関へ受診してください。
6. まとめ

以上、急性胃腸炎とはどんな病気なのか、急性胃腸炎の原因、その治療方法について紹介してきました。
適切な水分補給と食事管理、それに薬物療法などを適切に組み合わせることで、急性胃腸炎は多くの場合数日で回復します。ただし症状から自己判断した結果、別の病気であることを見逃してしまうこともあり得ますので、症状が重い場合また長引く場合には早めに医療機関を受診し医師の診察を受けることが大切です。
癌にならない腸活実践メルマガ講座
「癌にならない腸活実践メルマガ講座」では、がんで亡くなる人・苦しむ人を一人でも多く減らすために日常生活の中で実践できる
・免疫を上げる方法
・正しい腸活の知識
・腸内環境とお肌の関係
・健康的なダイエット方法
・乳酸菌のすごい効果
などを、腸の専門医が毎日メールでお届けいたします。
免疫力をアップして、いくつになっても健康的な毎日を過ごしたい方におすすめの内容になってますので、気になる方はぜひ記事下のバナーをクリックしてお申し込みください。
↓↓